※このシナリオはフィクションです。
2 【オレ】17歳 【彼女】17歳
「世界を平和にしようぜーーー! オレたちからだーーーーーーー!!」
オオオオオオ!!!
オレのシャウトに会場が応えた。オレのボーカルはすでに出番を終え、後奏はアイツのギターと彼女のキーボードが締めをつづる。酷使し切った喉の感覚と舞台の上でしか味わえない高揚が混ざり合い、非日常的な刺激にオレはしびれていた。
学園祭で初めて披露したこの三人のバンドは、登場でまず驚かし、演奏で心をつかみ、間断なく会場を熱し続けることで、その場に忘れられない激情を呼び起こした。オレも、アイツも、彼女も、その激情のど真ん中にいた。オレたち三人の特別な関係を確かめるのに十分な経験だった。
だから、オレはその関係の変化を、あるいは中断、もしくは終わりを、その後に繰り出した。
「オレは、卒業したらアメリカへ行く」
「……大学はどうする?」
興奮した三人だけの打ち上げの中、秘めていた進路を唐突に告げたオレに、アイツはもっともな質問を返した。
「大学は、行かない」
「大学……行かない……」
彼女はただ、オレの言葉を繰り返した。まだその言葉の意味が、理解できないかのようだった。
「オレは、世界を平和にすると、今日約束した。会場のみんなだけじゃなく、おまえたちや、オレ自身にも、曲で訴え続けてきたことだ。だが、今のままじゃそれができない。熱に浮かされた戯言で意味がない。オレは、それがイヤだ。そんなんじゃないんだ」
うまく言葉にできないオレの気持ちを、アイツも彼女も笑わなかった。オレ以上にわかっているのだ。
「受験が終わってから、大学を休学して行くのはどうなの?」
彼女の提案に、オレは首を横に振った。
「今、受験勉強に時間を使う気になれない。オレはもっと早く、曲を作り、曲を聴いて、歌いたい」
「じゃあ、日本でやればいいじゃない。今は音楽の方が大事なら、受験は来年すればいい。そうよ、そうすれば、私たちと一緒の学年になるし」
「ハ、誰も落ちなければな。いや、そうじゃない。オレはすぐにでも、アメリカの音楽に直接触れたいんだ。CDで聴くのとライブは違う。本を読むのと直接話すのでも違う。わかるだろう?」
オレは恥ずべき表現力の拙さを、二人とのつながりで補っていた。それで通じてはいる。だが、だからといって、オレの選択肢が直線ルートに限られる理由にはならない。それでも、オレにはどうしようもない焦りがあった。
「現実問題、お金はあるのか?」
「切り詰めて生活すれば、半年分。もちろんあちらでも稼ぐつもりだが」
「帰りの飛行機代は、その予算に入ってるの?」
「入ってない」
甘い見積もりを即座に見抜かれても、彼女の視線から目をそらさずに言えたのは、オレの意地の賜物だ。
「僕が小学生の頃、アメリカにいたことがあるのは知ってるよな? 僕の音楽は、そんなにおまえのよりも世界に響いているのか?」
「う……」
アイツもまた、オレの目を射抜くように鋭く見据えていた。動揺や嘘は、この二人に見逃されそうもない。オレは、動揺を隠そうとはせず、その代わりに嘘だけはつくまいと決めていた。
「オレは音楽で食べていくと決めているが、おまえはそうじゃない。だが、この際だから正直にいうが、オレはおまえの音や言葉、考え方にも嫉妬する時がある。そんな時、オレもアメリカへ行ければ、と思うことはある。たが、言っておくがオレのこの計画は、おまえと知り合う前から考えていたことだ」
「だから、留年しそうなほどバイトを頑張ってたのね?」
「そういうことだ」
二人はそこまで聞き取ると、しばらく沈黙した。
少なくともこれまでのところ、長期間オレと離れるのが寂しいから、という理由で引き止めようとする言葉はどちらからも出ていない。それは見込み通りで嬉しかったが、いじけて思う気持ちがにじみ出もした。
「僕はいずれ、お父さんの地盤を継いで、政治家になると思う」
それがアイツの将来の見通しだ。初耳ではない。
「僕はその責任をよく聞かされたから、自由なキミを見て、不公平だと思ったこともある」
これは初耳だ。
オレがアイツをうらやむことがあっても、アイツがオレがうらやむことなどあるはずがない、と誰もが口をそろえて断言するだろう。
「だが、キミたちと今日までやってきて、少し考え方が変わった。僕が期待されている将来の立場は、世界を平和にするためにできることがある。それが、今では楽しみになってきた」
それを聞いて、オレはニヤリと笑った。アイツも同じような顔で笑い返していた。
「その上で、僕はこう思っていた。大人になってからもこの三人で、一緒になって今日ステージで叫んだことを実現できたら最高だろうな、と」
「うん」
「ああ」
彼女もオレも、力強くうなずいた。
「だから、僕は友人としてだけでなく、将来的な事業の協力者としても助言をさせてもらう。キミには、大学卒業という資格をとっておいてほしい。その方が、将来できることが広がるはずだからだ」
「そうか」
オレはアイツの言葉を受け止めた。
「ウウゥ……」
無言のまま、食いしばるようにすすり泣きをもらす彼女の涙も汲みとった。
決心を後回しにして、この場の貴重で美しい真実を無駄にはしない。
オレは二人にこう答えた。
2Y「卒業したら、アメリカへ行く」
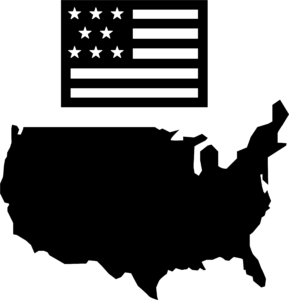
~【オレ】63歳 【彼女】62歳~
「まったく、頑固よねぇ。普通、あそこまで言われて考えな直さないものかしら?」
彼女は当時の切羽詰まったやりとりを、呆れた笑い話として振り返った。
雪はやむ気配がない。
「ほら」
背後から、オレに畳まれたままの傘が差し出された。
彼女の頭上ではすでに先程から、別の傘が広げられていた。
「僕の演説とキミの涙でも動かせないなんて、実際大したものだよ」
オレと彼女が高校での別れを物語っている途中から、アイツはやって来ていたが、ただ黙って聞いていた。
自分は背後で立ったまま、座っている彼女を雪から自分の傘で守っている。こんなキザなことが様になる奴だった。
「アメリカ、行ってよかったよ」
オレは後悔をしていない。
今と違い、日本とアメリカで連絡を取り合うのは高くついたが、オレたちの関係は海をまたいだくらいで疎遠になったりしなかった。
そして、若い頃のアメリカでの体験は、オレの深い部分で血肉となっている。
渡米期間は半年で切り上げたが、その後にオレは日本でミュージシャンとして、メジャーデビューを果たすことができたのだ。
2N「受験勉強には、協力してくれるか?」
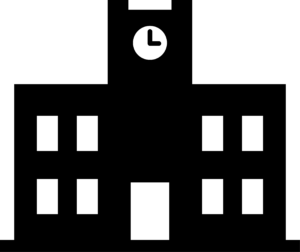
~【オレ】63歳 【彼女】62歳~
「二人にはかなわない」
当時、降参したことを思い出しながら、オレは実際に両手を上げて見せた。友人からの誠実な説得も効いたが、特に美人の涙には抗えない。
「フッ」
先ほどから無言で、オレと彼女の背後に立って話を聞いていたアイツが笑う。
雪は降りやまない。
「ほら、二人とも持って出なかっただろう」
アイツはオレと彼女にそれぞれ傘を渡し、自分の傘も開いた。
オレと彼女は左に移動して、アイツのための場所を作った。彼女を真ん中に、傘を差しながら三人で木のベンチに座る格好になる。そうしていると、昔の関係を身近に思い起こすことができた。
オレは一度、この関係を壊してしまった。
アメリカ行きを中断して、アイツにしごかれ彼女に応援されて、オレは大学受験に受かることができた。だけど、その後にアメリカへ行くことはなかった。
大学に通いながら、日本でのバンド活動が軌道に乗ったため、投げ出すことができなくなったのだ。だが、あの時アメリカへ行っていれば、もっと世界は広がっていたんじゃないか、と思うことをやめられなかった。
そうしたオレの鬱屈は、彼女とアイツにも伝わった。彼女は、オレとは別の大学に進学し、在学中すでに、モデルとして注目を浴び始めた。アイツは、苦労して名門大学に入学し、そこで必要な学問を修めるのに忙しくなった。
オレたちの時間は、三人一緒には使われなくなっていった。
それでも、少々の八つ当たりでは揺るがないアイツとは、たまに用事があると声をかけ合うような仲が続いた。
だが、繊細な彼女との距離を測るのにオレは慎重になり、近づきすぎては逃げるのを繰り返した。オレが彼女から逃げた何度目かの後、振り返ると彼女もまた、背を向けていた。
彼女を癒やし、寄り添える場所にはアイツがいた。それは理にかなっていることだと思えた。



コメント