
ホントに宇宙行っちゃったよ!

すごいね

僕と同じ世代だよ!

夢があるような悔しいような……

僕たちだって、まだまだこれから!
できることからやっていこう

オー
今回は少し脱線して、昨年末話題となった夢のあるニュースにインスパイアされて、分岐型小説を書きました。
全5回です。
最終回で、分岐結果の状況に応じた年金請求時の添付書類を紹介します。
お付き合いいただけたら幸いです。
※このシナリオはフィクションです。
あの約束を忘れない
1 【オレ】63歳 【彼女】62歳
店を出ると、途端にキリリとした冷たさが、身体を覆う湿った暖気を断ち切った。
それでも、身体の中のぬくもりはまだ当分冷めそうにない。むしろ、熱いくらいだ。
だから、オレはコートも取らず、店の外に出た。
来た時には気配もなかった雪が、いつの間にか視界を埋め尽くす勢いで降っていた。道路のアスファルトは無事だが、その先の林に地面には、すでにうっすらと白く積もり始めていた。
これは、この後どうにかして家に帰ろう、という気持ちをなえさせる。それも見越してだろうか、今も懐かしい顔ぶれが騒いでいる背後の民宿兼居酒屋は、時間制限なしの貸切にされていた。優秀な幹事は、何十年ぶりかの同窓会を、日付が変わる前に切り上げさせる気などさらさらなかったのだ。
「うわ、雪が降ってる。きれいね」
ガラリ、と店のドアが開くと同時に、聞き馴染んだ声が聞こえた。
振り向くと、彼女はほんのりと朱みを差した頬に微笑みをのせて、傘も取りに戻らず、まっすぐこちらに歩いてきていた。
オレは、なかなか風情のある丸太を削ったベンチに腰掛けたまま、その隣のかすかな雪を手で払い、場所を作った。
「ありがとう」
彼女はそう言いながら、手に持っていたコートをオレの肩にかけてくれた。それは間違いようもなく、オレのコートだった。
彼女が座ると、オレが作った場所は思ったよりも距離が近いことに気付いた。この寒さなのだからいいだろう。
「よく一人で抜け出せたね?」
彼女は常に人を惹き付ける人気者だ。
昼過ぎから少人数で始まって、その後、次第に集まる人を増やしてきた時間の中でも、最も盛り上がったのは彼女の登場シーンだった。それ以来、彼女は大勢に囲まれ通しだった。
「そりゃあ、私もパーティーには慣れているもの。抜け出し時は心得たものよ……なんて。みんなもいい大人になったのよ」
「そうかな? あまり、変わってないように思ったけど」
それが、オレの正直な感想だった。
中には会うのが40年ぶりという顔もあったが、酒が十分に回った頃には、高校時代に鮮明な時間を一緒に過ごした奴らが帰ってきたように思えていた。
それは不思議でもあり、やっぱり腑に落ちることでもあった。
「アイツも、変わらない」
オレは、本心からそう言った。
「そうね。彼も、貴方も、変わらない」
彼女も当然、同意をした。
今日の同窓会は、アイツがきっかけだ。無理に時間を作って早めに参加をしていたアイツは、彼女のようににぎやかな登場シーンこそなかったものの、本来この集まりはアイツのためのようなものだ。高校の同じクラスの中から『内閣総理大臣』が出たのだから。何十年も眠ってホコリをかぶっていた連絡網も、それは息を吹き返す。
そして、驚くべきことに、アイツは同窓会の参加を承知した。それも、就任間もない今の時期に、だ。恐るべき強引な日程調整だったろう。周りの人間の苦労がしのばれる。
ただし、アイツはクラスが違うどころか学年が1つ上のオレの参加も、提案したらしい。当時のオレたちの関係を知っている幹事は、快くオレにも声をかけてくれた。
そんな集まりなら、オレだって少々の厚かましさを承知で参加したい。アイツほどでは到底ないだろうが、相当な無理を通して参加することにした。
昔は民宿だけを営んでいたこの民宿兼居酒屋を会場に指定したのも、アイツだと聞いている。
「この店も、建物は当時のままよね」
「ああ」
この丸太を削ったベンチも、当時のままだ。
~【オレ】16歳 【彼女】15歳~
長い坂道を、自転車でペース配分も考えずに登ってきたため、足の筋肉が動かなくなってしまった。ぜーはーと呼吸を繰り返す肺の痛みも相当だ。
仕方なく足を止め、ハンドルに上半身の体重を預けると、オレの顔から汗がぼたぼたと落ちる。日中は、体温とほぼ変わらない気温の中で自転車を飛ばし、ここまで来たのだ。夕日が沈んで直射日光こそなくなったとはいえ酷使を続けて灼熱を帯びた身体は今にも燃え上がりそうだ。
こんなに必死になってまで、オレはどこに向かっているのだろう? この曲がりくねった山道の先には、ほとんど地元の人間だけが使うボロい民宿しかない。今は、オレの高校の野球部が合宿所に使っている。いや、今日と明日に限っては、野球部と、ダンス部とが合同で合宿しているのだ。 野球部には、アイツがいて、ダンス部には、彼女がいる。
その予定を聞いた時、オレはふうんと相槌を打つだけだった。一緒に来ない? と彼女に誘われても、すげなく断りさえした。オレは、野球部でもダンス部でもないからだ。その合宿になど、行く理由がない。
それなのに、オレは今日になっていても立ってもいられなくなり、自転車をここまで一気に走らせていた。その距離を考えると、狂気の沙汰といえる。今、知ってる顔に出会い、何してるの? などと聞かれでもしたら、なんと答えればいいのやら。
カブトムシを取りに来た、と答えようと決めてはいる。
わざわざこんな遠くまで? と問いを重ねられても、オレ以上にカブトムシのことに詳しい奴はそういないので、なんとでもごまかせる。ごまかせそうもないのは、オレが自慢気にカブトムシの捕り方をよく話して聞かせたアイツと、もしかしたらそれを隣りで聞いていた彼女だけだ。
二人のことを思い出すと、足の筋肉に活力が戻った。肺の回復はそれ以上に早い。ロックバンドのボーカルで鍛えた自慢の肺活量なのだ。
顔を上げ、曲がりくねった山道の先に小さく見える民宿所を遠目に見た。たどり着くには、まだ時間がかかる。だが、すでに視界に入ってはいる。
「ん?」
よく見ると、宿の外に人影があった。二人の人影。
それが、あの二人だと気付くと、心臓がビョコンと跳ねた。オレは動きが止まり、息をひそめてその人影を見つめた。声など、もちろん聞こえない。ベンチで寄り添うようにして座って動かないその人影を、どれだけ見つめていたのだろう。
やがて、二人は連れ立って宿に戻っていった。
宿の中には、他にも野球部やダンス部の連中がいるはずだ。二人は、二人きりでの話をもうしないだろう。
オレは、今度こそ民宿所に向かう目的をなくして、下りになる坂道を戻っていった。風を切ると涼しいが、暗い山道で考えなしに自転車を走らせるのは冗談でなく命取りなので、きちんと注意深くブレーキは使っていった。
次の日の夜遅く、オレの家の電話がジリリリと鳴った。
受話器は家族が取る前に、オレがとった。
「はい、もしもし」
〈……〉
電話の相手は無言だった。
オレには、相手の予感があった。しかし、喉の奥の方で何かが膨らんで詰まってしまい、声が出てこない。
受話器を持ったまま、あちらとこちらをつなぐ沈黙が育って脈打っていた。
〈昨日、見てた?〉
どれだけか経ってから、彼女の声で、受話器からそう聞こえた。見てたのを見られてた、と思うと、自分の顔が紅潮するのが分かって、オレはとっさに答えた。
1Y「見てた」
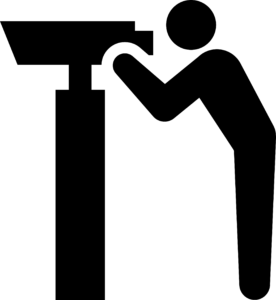
〈彼にね、好きだって言われたの〉
予想していた通りの言葉だったが、オレはついカッとなった。
「おまえを好きになったのはオレが先だ!」
かすれ声になどなら内容気を付けながら、オレは彼女の話の先を遮るように言った。オレは、もっと早くそれを言ってなければいけなかった。
〈そんなこと、初めて聞いた〉
「それでも、知ってたはずだ。中学の頃から、おまえの姿を見るためにだけ、学校に通っていた」
〈なあに、それ〉
電話口の向こうで、彼女はフフフと笑っていた。
「気付いていたはずだ。昨日の視線だって気付いたぐらいだ」
〈……うん、気付いてた〉
オレと彼女は、中学から同じだった。しかし、学年が違って接点もなかったため、有名な学校一の美人を、オレは遠目に見るだけだった。時々目が合った気がするだけで、その日は学校に来た甲斐があったと舞い上がったものだ。
思いがけず彼女との距離が近付いたのは、アイツが来てからだ。オレと彼女が中学からエスカレーター式に進学したその高校は、名門私立大学への推薦枠をもつ中高一貫校だ。高校に外部から入ってくるのは、相当優秀な成績がなければいけない。アイツはそんな、外部から入学してきた一年生だった。
オレはといえば、その昨年にバイトやバンド活動に夢中になり、出席日数が足らずに赤点を連発し、追加の課題やらをこなして、ほうほうの体で進級したようやくの二年生だった。
成績もトップクラスで、野球部でも一年生の中で頭角をあらわしていたアイツと言葉を交わしたのは、あの日の校舎裏が初めてだった。
一人で、思いついたフレーズを口付さみ、いつも持っている白紙のメモ帳に書きつけ終えた後、突然声をかけられたのだ。
それは誰の曲ですか、と。
話しかけた相手があまり行儀の良くない上級生とわかっても、アイツは怯えなどかけらも見せず、丁寧な物腰で踏み込んできた。オレは腹立ちを隠さなかったが、嘘をつく習慣はないので、正直に、オレの思いつきだと答えた。曲にはまだなってない。
それを聞いて、アイツは心底驚いたようだった。こちらから聞いてもいないのに、自分も楽器をやっていて、作曲も独学で勉強しているのだと教えられた。オレも、学校内でそうした話をする相手に飢えていたのだろう。同好の相手との会話は、お互い相手が話し終わるのも待たずに、まくしたてるような調子ではずんだ。アイツは、野球部の練習開始時間を忘れて遅刻してしまった。
その校舎裏での関係は、次の日も続いた。やがて、オレとアイツは校内で顔を見かければところ構わず話し込むのが当たり前の、異色の二人組と周囲に知られるようになっていた。
その二人組はすぐに、野球部の応援を通じてアイツとよく話すことのあった、同じクラスでダンス部の彼女も加えて三人組になった。
そんな三人の関係はできあがってばかりで、まだ形も固まり切ってない夏の終わり頃に、あの合宿はあった。アイツは明言こそしなかったが、その合宿で彼女に告白することを、誤解の余地なくオレに前もって伝えていた。オレは、そのことに気付かないふりをしていた。
それなのに、その話を実際に彼女から聞かされると、オレは視線と態度だけで通じ合っていると妄想していた気持ちを、それまでとは一貫性のない言葉であからさまにした。
〈私も、先輩のことは気になってたから〉
その妄想が現実のものだと彼女に告げられた時、オレはとんでもないような嬉しさとともに、アイツへの後ろめたさを感じずにはいられなかった。
彼女がアイツにどう返事をしたのかは、オレは今でも聞いてはない。ただ、彼女と付き合うことになったことをオレからアイツに告げた時、アイツはいつもの冷静な態度を崩さず、そうか、とだけ答えた。
それからも、俺と彼女の引け目など存在しないように振る舞うアイツのおかけで、奇跡のような三人組の関係は続いた。
1N「なにを?」
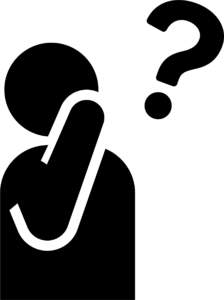
〈ううん、なんでもない〉
彼女はそう言って、突然の電話を謝り、受話器を置いた。その間オレは、うん、とか、ああ、としか言えてなかったと思う。
ダンス部よりも期間の長い野球部の合宿が終わってすぐに、オレはアイツから律儀に、彼女と付き合うことになったと聞かされた。そもそもが、同じクラスのアイツと彼女のつながりがあり、オレが後から加わった関係だ。二人がより親密になろうと、オレが口をはさむいわれはない。
オレと彼女が友人と呼べる間柄になったのは、アイツが来てからだ。オレと彼女が中学からエスカレーター式に進学したその高校は、名門私立大学への推薦枠をもつ中高一貫校だ。高校に外部から入ってくるのは、相当優秀な成績がなければいけない。アイツはそんな、外部から入学してきた一年生だった。
オレはといえば、その昨年にバイトやバンド活動に夢中になり、出席日数が足らずに赤点を連発し、追加の課題やらをこなして、ほうほうの体で進級したようやくの二年生だった。 成績もトップクラスで、野球部でも一年生の中で頭角をあらわしていたアイツと言葉を交わしたのは、あの日の校舎裏が初めてだった。
一人で、思いついたフレーズを口付さみ、いつも持っている白紙のメモ帳に書きつけ終えた後、突然声をかけられたのだ。
それは誰の曲ですか、と。
話しかけた相手があまり行儀の良くない上級生とわかっても、アイツは怯えなどかけらも見せず、丁寧な物腰で踏み込んできた。オレは腹立ちを隠さなかったが、嘘をつく習慣はないので、正直に、オレの思いつきだと答えた。曲にはまだなってない。
それを聞いて、アイツは心底驚いたようだった。こちらから聞いてもいないのに、自分も楽器をやっていて、作曲も独学で勉強しているのだと教えられた。オレも、学校内でそうした話をする相手に飢えていたのだろう。同好の相手との会話は、お互い相手が話し終わるのも待たずに、まくしたてるような調子ではずんだ。アイツは、野球部の練習開始時間を忘れて遅刻してしまった。
その校舎裏での関係は、次の日も続いた。やがて、オレとアイツは校内で顔を見かければところ構わず話し込むのが当たり前の、異色の二人組と周囲に知られるようになっていた。
その二人組はすぐに、野球部の応援を通じてアイツとよく話すことのあった、同じクラスでダンス部の彼女も加えて三人組になった。
そんな三人の関係はできあがってばかりで、まだ形も固まり切ってない夏の終わり頃に、あの合宿はあった。アイツは明言こそしなかったが、その合宿で彼女に告白することを、誤解の余地なくオレに前もって伝えていた。オレは、そのことに気付かないふりをしていた。
だから、あの日見たことも、気づかないふりをするのが一貫した態度だったはずだ。
幸い、アイツと彼女はオレの前では、付き合っている素振りを一切見せることがなかった。
だから、オレは三人の関係を大切にしたまま、高校生活を続けることができた。



コメント