
精神科の先生が、診断書を出すから会社を休んだほうがいいって

それがいいよ

でも、お給料がなくなったらどうすれば……

社会保険から「傷病手当金」が出るから、しばらくは大丈夫だよ

「傷病手当金」?

うん
病気で働けなくてお給料が出ないときに、お給料のだいたい3分の2の金額をもらうことができるんだ
精神科でうつ病等の診断書が出るような状態でも、会社に休職を切り出すのにはするのには不安が伴います。
将来の不安も大きいですが、多くの会社では休職中の給料は出ないため、当面の生活費の不安にも悩まされます。
そこで、会社勤めで社会保険に加入しているなら、「傷病手当金」という制度を利用します。
これは、病気やケガを療養するために働けなくなって、給料が出なくても、最長で1年6ヶ月は給料の約3分の2の金額が受け取れる制度です。
しかも、一定の条件を満たしていれば、退職後も受け取り続けることができます。
この記事では、そのことを知っているのと知らないのとで、その後の人生を左右するかもしれない「傷病手当金」についてご紹介します。
[この記事で解決したいお悩み]
- 精神科の先生に休職を勧められるけど、生活費が不安で休めないという方に、「傷病手当金」を知ることで安心して休職してほしい
- 休職よりも退職を考えている方に、「傷病手当金」は退職後も一定の条件で受け取り続けることが出来ることを知って、将来設計に役立ててほしい
「傷病手当金」とは
病気やケガによって、会社を長期に休んで給料が出なくても、社会保険には「傷病手当金」という制度があります。
「傷病手当金」をもらうための条件は、3つあります。
- 業務外の理由による病気やケガの療養中であること
- 働くことができないこと
- 連続した3日間を含む4日以上、療養のために仕事を休んでいること
以下に、それぞれの条件をもう少し補足します。
1.業務外の理由による病気やケガの療養中であること
この条件に「業務外の理由」とあるのは、健康保険と労災保険の区別のためです。
今回の記事で紹介する「傷病手当金」は、前者の健康保険によるものです。
仕事がイヤになってうつ病になったのは果たして「業務外」と言えるのか? と疑問は湧くかもしれませんが、業務上でよほど特別な心理的負荷がかかる出来事があり、かつ個人的な事情による発病ではないといえない限り、労災保険の適用が認められるのは難しいのです。
そのため、うつ病になった理由が少なからず職場にあると思う場合でも、多くの場合、健康保険の「傷病手当金」を請求していると思われます。
ただ、一般的に健康保険よりも労災保険のほうが補償が手厚いので、病気になった原因が明らかに職場にあると考えられる場合は、労働基準監督署などに相談したほうがいいでしょう。
逆に、労災保険の適用を考えていないのであれば、健康保険の「傷病手当金」の申請書を書く際には、病気になった原因が会社にある、などという主張は書かないほうが無難だと思います。
「業務上」の病気であるなら、「傷病手当金」の支給対象ではないのではないか、と協会けんぽ・健保組合の審査段階で問い合わせなどが入り、決定までに時間がかかることが考えられるからです。
申請書には医師が記入する欄もありますが、本人の強い主張がない限り、「発病または負傷の原因」は「不詳」のように書かれると思います。意に沿わない記載があれば、提出前に医師に相談しましょう。
2.働くことができないこと
ここでいう「働くことができない」(条文上は「労務に服することができない」)とは、その人の本来の職場での仕事ができない状態を指します。
つまり、本来職場と関係のない、比較的負担の軽い活動ができるとしても、元々の仕事ができない状態なら、この条件にあてまるということです。
ただし、どこまでの活動が元々の仕事よりも軽い負担なのかは、線引きが難しいところでしょう。
退職も見据えての休職の場合、転職活動や資格の取得などを休職中にやっておきたいという焦りが出るかも知れません。
実際にそうした活動をしたいと思ったら、まずは医師にご相談を。
ただし、医師も傷病手当金の給付判断や職場の対応までは断言できないと思います。
そうした活動が職場に知られてしまった場合の心配がふくらむようでしたら、じっくりと療養に専念したほうが良いかも知れません。
3.連続した3日間を含む4日以上、療養のために仕事を休んでいること
医師から「労務不能」の診断書が出て会社を休み始めたとしても、1日目から「傷病手当金」の支給対象になるわけではありません。
連続して最初の3日間(「待期期間」といいます)は支給の対象にならず、4日目から「傷病手当金」の支給の対象になります。
「連続して」の条件があるので、2日休んで、1日会社に出て、その次の日に休んで、という通算3日の休みでは、この条件を満たしません。休みが「連続」せず、途切れているためです。
なお、土日・祝日や有給休暇は待期期間に含めることができます。つまり、有給休暇を使って休みに入れば、有給休暇と土日・祝日も含めて連続した3日間で、給料をもらいながら待期期間を完成させることができます。
そして、有給休暇ではない、その次の日の給料の出ない休み(休職)から、「傷病手当金」の支給対象となります。
退職後も傷病手当金をもらう条件
退職後も「傷病手当金」がもらえることは、意外と知られていないかもしれません。
そのための条件は、下記の2点です。
実際にそういった状況にある方は、誤解のないように自身の加入する協会けんぽ・健康保険組合に確認してください。
- 退職日までに継続して1年以上の被保険者期間 があること。
「継続して1年以上」なら、同じ会社でなくても構いません。
ただし、健康保険の被保険者期間の喪失日と取得日の間が1日でも空いていると、それは継続していないということになります。
また、この条件にある被保険者期間から、任意継続被保険者期間(退職後に、任意で、全額自己負担による健康保険に継続加入した期間)は除かれます。 - 資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。
最後のごあいさつとばかりに退職日に出勤してしまうと、「労務不能」ではなくなったということになってしまい、退職後に「傷病手当金」を受ける権利を失います。
これは、職場の労務担当が知らなければ実際にあり得るので、恐ろしいことです。
退職日は出勤しないよう、職場と調整しておきましょう。
また、退職後に初めて「傷病手当金」を請求するのであれば、退職日の前日以前に3日間の待期期間を完成させておかないといけません。
退職日の前日以前に、労務不能の診断を受けた上で、3日間連続の休みをとっておきましょう。
休職から傷病手当金請求までの一例
休職の入り方
病院の先生から休職を勧められた場合、そのための診断書を即日作成していただくか、それともその日に診断書はお願いせず、先に職場にそのことを話すかを考えます。
医師から仕事を休んで療養するよう勧められたら、すぐに診断書をもらって、次の日から休職に入るのが一般的だと思います。
ただ、残務整理や引き継ぎのことを考えるとそれはできない、と考えてしまうようなら、先生とも相談の上、診断書の発行を後のばにできるか相談してみましょう。
ちなみに、復職を念頭に置いているのであれば、有給休暇は休職前に全部は使い切らないほうがいいかもしれません。
なぜなら、有給休暇は所定労働日の8割以上出勤していないと付与されないことが多いので、休職が長くなった場合、復職してから次のタイミングで有給休暇が付与されず、1年間以上自由に休みが取れないことになってしまうからです。
(有給休暇の付与日が毎年4月1日だとすると、前年度の4月1日~翌年3月31日の間に2割の期間を超えて休職していると、次の4月1日に有給休暇がもらえません)
これは、なかなかシビアな話ではないでしょうか。
目安としては、5日〜10日程度は残しておいた方が、復帰の後が楽かもしれません。
傷病手当金の申請手続きの流れ
「傷病手当金」の申請書は、会社からもらえるのを待ってても、本人から申請するものだから、ともらえないかもしれません。
その場合、自分で協会けんぽ・健康保険組合のホームページから様式を印刷をするか、電話して送ってもらうかしましょう。
ホームページから様式を印刷する場合、A3の様式を印刷できるプリンターは家になかなかないと思いますが、コンビニのネットプリントサービスでデータの印刷が可能です。
コンビニでA3の両面印刷をする場合、カラーだと高く付きますが、白黒だと安くすみます。
そうして「傷病手当金」の申請書を入手した後は、
- 本人の記入
- 医師の記入
- 会社の記入
- 協会けんぽ・健保組合で受付・審査
という流れになります。
2→3の流れは、医師に記入していただいてから、本人が会社へ郵送なり持ち込みなりで届けます。
3→4の流れでは、会社から協会けんぽ・健保組合に送ってくれるはずです。
なお、退職後の「傷病手当金」の申請で、支給対象に在籍期間を含まないのであれば、3の「会社で記入」は不要のため、2→4へ本人が直接提出します。
「傷病手当金」の申請書で悩む欄の書き方
初めて書くときに迷いそうなのが、「申請期間」と「申請期間に報酬を受けましたか」という欄の書き方です。
具体的には、ご自身が加入している協会けんぽ・健康保険組合に直接電話で聞くと、教えてもらえます。
その前の予備知識として、一般論でここではご説明したいと思います。
まず、「申請期間」については、無給になる休職日(有給休暇や土日祝日の後の日)から逆算して、連続する3日間の待期期間の1日目から、とします。
次に、「申請期間に報酬を受けましたか」は、「申請期間」に待機期間が混在したり、休職期間に一部の手当が出ることもあるので厳密に書くのは難しいと思いますが、通常は、会社の証明で支給額は決まるため、休職中は給料が払われないと会社から聞いているのであれば、報酬は受けられないと書けばいいと思います。
なお、実際に休職期間中に一部手当が出ていた場合、これら会社からの支給金額は、「傷病手当金」の支給額から差し引かれます。
また、「発病時の状況」なども、ご自身で考えると難しいと思いますが、「自立支援医療」用の診断書のコピーを取っておけば、先生の書き方を参考にして書くことができます。
「傷病手当金」の手続きから振り込まれるまでの期間
「傷病手当金」の請求は、短い期間であれば復職後にまとめてでも良いのですが、長期の休職であれば、1ヶ月ごとの請求が標準的のようです。
「傷病手当金」申請書の入金までに要する期間は、医師で1週間、職場で1週間として、協会けんぽ・健康保険組合では2週間程度なので、最短でも1ヶ月程度かかります。
なお、休職中に1ヶ月に1度も診療記録のない月があると、医師による記入欄を書いていただきことができなくて、その期間の「傷病手当金」が「不支給」になる恐れがあるため、医師から指示された通院の予約は欠かさず守るようにしましょう。
傷病手当金は1傷病につき1回のみ
「傷病手当金」が受け取れるのは、前述の通り最長1年6ヶ月です。その後は、原則として同じ理由で傷病手当金は受け取れません。
例えば、「傷病手当金」をもらいながら1年6ヶ月間休職して、その後復職したけれど、翌月にはまたうつ病の症状が重くなり、会社で働けなくなったとします。
この場合、残念ながらすでに同じ「うつ病」で「傷病手当金」をもらい初めて1年6ヶ月を過ぎてしまっているので、同じ「うつ病」ではもう「傷病手当金」をもらうことができません。
ただし、復職してから相当の期間にわたって医療(予防的医療を除く。)を受ける必要がなく、通常の勤務をしてから再び「うつ病」になったような場合、「社会的治癒」(※)の主張を考慮してもいいかもしれません。
前回「傷病手当金」を受け取ったうつ病と、今回の「うつ病」とは別の病気だから、「傷病手当金」をもらう権利はある、という理屈での請求してみるということです。
それが認められるかどうかは、個別に審査されることになります。おそらく通常の請求は「不支給」となるため、審査請求や再審査請求での争いになると思います。
※「社会的治癒」とは:病気の症状がほぼなくなり、投薬等の治療を必要とせず、一般的な労働を一定程度継続していた場合に、医学的治癒とは区別して認められる考え方。
まとめ

「傷病手当金」の申請書を出すことで、わたしが病院で話したこと、会社に変なふうに伝わっちゃわないかな?

大丈夫!
病院の先生はお姉ちゃんの味方だから、書いて欲しくないことは書かないよ
もし気になる部分があったら、会社に提出する前に目を通して、直してもらえばいいよ」

それなら安心、かな?

よかった(^^)
病院の先生は味方です(味方と思えない先生なら、転院を検討していいと思います)。
心配なことは、どんどん相談しましょう。
だけど、「自立支援医療」や「傷病手当金」などの制度は自分で知らなければ、相談もできません。
そのための情報を、本ブログでは紹介していきたいと思います。
※2022年1月1日からの法改正で、「傷病手当金」の1年6ヶ月の支給期間が、支給開始からの経過期間から、支給のあった期間の通算になるそうです!(本記事作成はそれより前)
これでどう変わるのかという、例えば、まず1年間休職して「傷病手当金」をもらい、一旦復職し、その1年後に同じ病気で体調を崩して再度休職した場合を考えてみます。
この場合、現行では再度の休職時には、最初の「傷病手当金」の支給開始から1年6ヶ月を経過しているので「傷病手当金」もらえませんが、法改正後は、最初に1年分もらったとして、残る6ヶ月分は2回目の休職でもらえる、ということになります。
適用対象は、2021年12月31日に、傷病手当金の受給開始から1年6ヶ月経過していない場合ということです。
これから休職に入る、復職を考える人などには大きな影響があるので、施行までにより具体的な情報が出てくれば注視しましょう。
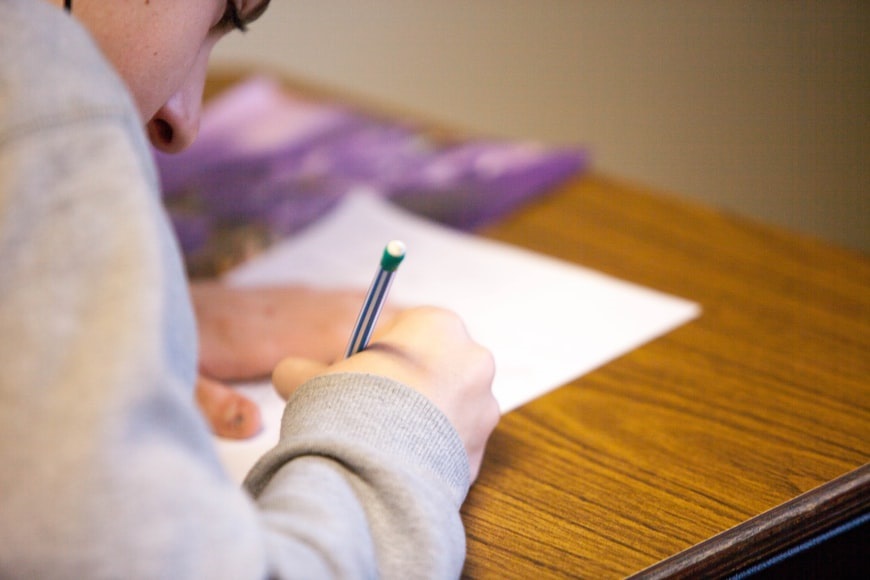


コメント